はい。きました。その5。
あと半分続くから我慢してね。
ひとりごととはなんぞや
というかたは
ひとりごと1をごらんくださいまし。(リンク)
昔の原文(に少し修正したもの)
ぼくの大いなるひとりごと。PART 5
~「わかりやすい・わかりにくい」とは~
これは僕の頭の中にある「面白いなぁ」を徒然書いたものです。
なので、先行研究や学術的根拠はないです。
特に興味のない人は折り紙にして日本文化を堪能して下さい。
今回は、「わかりやすい」についてのひとりごとです。
昔から「わかりやすい」とはどういうことか
に
興味を持っていたので少しだけ考えてみたいと思います。
人に物事を伝える時って、
分かりやすくするためにたとえ話をするじゃないですか。
でもそれって本当にわかりやすくするために役立つのでしょうか?
自分を含めて多くの人は、
「例えば」と切り出すことになんの抵抗もなく、
むしろ会話の技術として使っていますよね。
でもこれは一体何故なんでしょうか。
例えば(ほらここにも)、
皆さんもこんな言葉どっかで聞いたことがあると思います。
「みて下さい、この広さ!なん東京ドーム3つ分です!」って。
なにか拾い物や大きいものを比喩する時に、
東京ドームがよく使われいるイメージがあります。
つまり、東京ドームというのは、
「広い場所」を測る基準のように使われているわけですね。
でもそもそも
東京ドームの広さってわかりますか?
僕は東京生まれですが、みたことありません。
多分、でっかいんだろなぁ、というくらい。
つまり何が言いたいかというと、
わかりやすく伝えるために様々なたとえ話や比喩をすることがありますが、
それは得てして大まかな情報を伝えるに過ぎないのです。
つまり、その事物の中心要素には届いていない。
そうなってくると、
「わかりやすい」ということは「なんとなーくわかる」ことと、
紙一重なのではないか。
ということです。
でもそれでいいのです。
それこそがわかりやすいということなのではないか。と。
東京ドームの広さを知っている人がそんなに多くないにもかかわらず、
よく比較対象としてあげられるのは
みんながなんとなく広いということを知っているからに他ならないのではないかと。
「小さな親切、大きなお世話」という言葉がありますが、
道案内をする時に、あまりに細部まで教えてしまうことにより、
かえって混乱してしまうということがあります。
教える側は良かれと思って細かく教えるのですが、逆効果になってしまう。
それと同じなのではないでしょうか。
つまり、(時と場合によりますが)教えて欲しい側は
大体のイメージを掴みたいわけであって、
そこまで詳細にわかりたいわけではないのかもしれません。
ここを20M歩くとOOというお店が左手に見えて来て、
そこをさらに歩くと、
電柱がある十字路に出ます。左にはコンビニがあります。
そこを右に曲がると目的地です。
これって要は、
ここをまっすぐ行って、角を右に曲がる。
でいいわけですよね。
そもそも、例え話って、ある事物を他の事物で説明するわけですよね。
その段階で元の事象が100%理解されることはあり得ないのではないか。
100%に近づけようとすればするほど、ややこしくなり、結局離れていく。
要するに、「わかりやすい」ということは、細部まで伝えることではなく、
その大まかな要素をシンプルに伝えていることなのではないでしょうか。
沢山説明したがる人は「話し下手」とよく聞きますが、
わかりやすく話す人は、シンプルに重点を伝えていることに気づきます。
えー紙幅の関係上、終わります。
このひとりごとがわかりやすいのかどうかは
この際エレベストの上にでも置いといてください。
ではみなさま、良い夏休みを!
「次は価値観について」、です。
現在の僕の考察
あーそうか。これを書いたのは夏休み直前だったんだなぁ。。
なつかし。
さて、始めましょう。
まず、えーっとどうだろう。
すごいわかりにくいよね。この文章。
わかりやすいとはなにか。
ということを説明する文章がわかりにくい。
致命的な自己矛盾。
ということで、フォローしていきましょう。
まず、趣旨としては「わかりやすいとは何か」を考えること。
そして、結論としては、
「わかりやすい」に必要なのは、
情報量が少なく、シンプルにゴールが見ていることなわけです。
広さを伝える場合でも、
この建物の面積は、
OO平方センチメートルで。。あーだこーだ。。
ではなくて、
東京ドームが20個分なんです。
だけでいいと。
実際に東京ドームの大きさがどうかとは別に気にしなくていい。
シンプルに、
あ、じゃあかなりおっきいんだね。
だけ分かればいいわけですもの。
要は伝えたい、知りたい情報のコアは、「大きい」ということで、
他の情報はそれの補足に過ぎないわけで。
細部まで、その情報を伝えようとすると、
そのコアが隠れてしまう。そうすると、「わかりにくい」
ということになるのではないか。
というのが当時の僕の結論であります。
一言でまとめると、
わかりやすく伝えようという人は話し過ぎ。
諦めろ。ということです。
比喩する時は
「おっきいんだね」くらいが伝わればそれでいい。
例え話をするならば、
100%近づけようと思うな。50%くらいでいい。
最終的な目的は
その表現たちが補おうとしている情報のコアを伝えることなのですから。
ということなんじゃなかろうか。
ちなみに僕はこの「わかりやすい」「わかりにくい」について
考えていることが多い。
時には外国語の手を借りて、
時には哲学の手を借りて、
でもいまだに答えは出ない。
わかるということはどういうことなんだろうか。
「わかりやすい」と「わかる」ということは
因果関係にあるのだろうか。
なんてことを改めて思い出しました。
ありがとう。昔の僕。
あ、6年前、家庭科の授業で感じた
わかりやすさについてはこちら
おもしろい視点である。と思う。
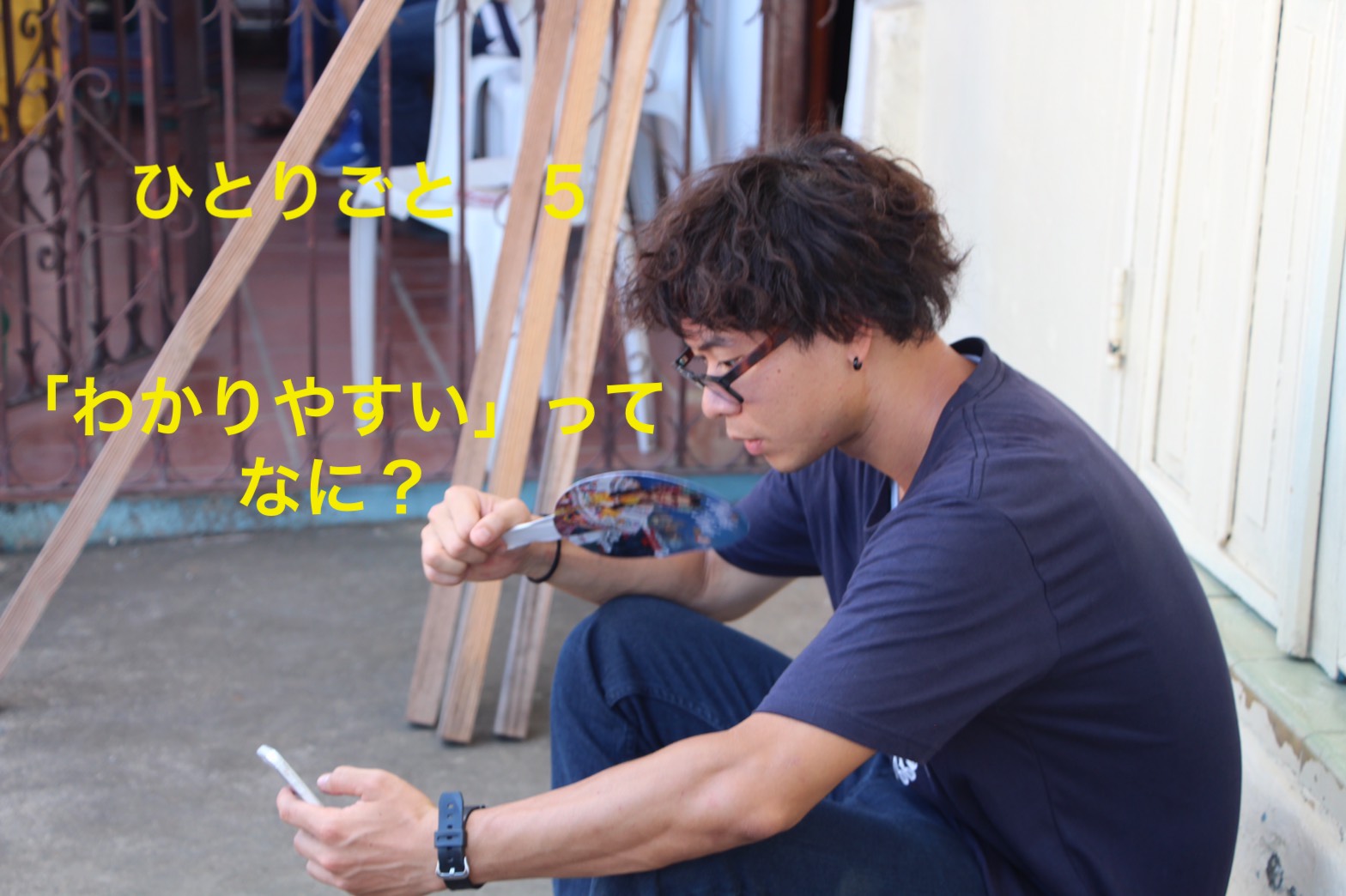


コメント